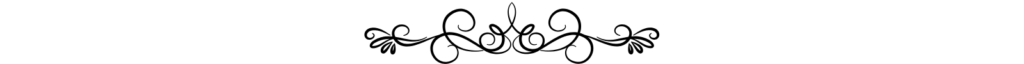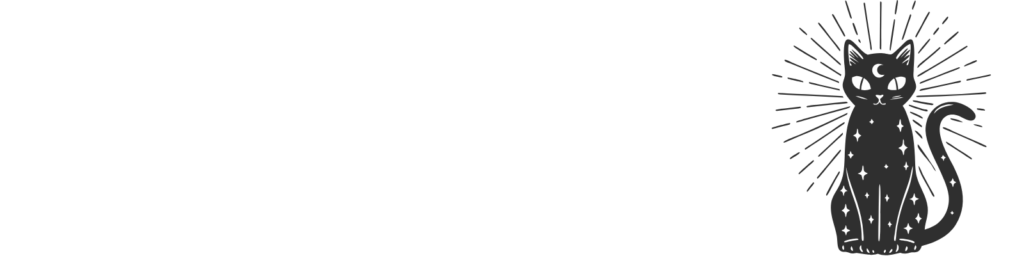第四章:星の記憶と、ひとつに還る歩み
塔が崩れたあと、世界は静かだった。
風も音もない場所で、愚者はうずくまっていた。
すると、夜空に小さな光が生まれた。
それは「星」。
やわらかく瞬きながら、何も語らず、ただそこに在った。
愚者は目をあげた。
悲しみのあとに、希望は声を出さずやってくる。
星は、願いを叶えるのではなく、願う力そのものを思い出させてくれる存在だった。
星の下を歩くと、景色が揺らいで見えた。
「月」が昇っていた。
銀色の川、姿を変える影、遠くの吠える声。
愚者は戸惑った。何が本物で、何が幻なのか。
月は語らず、ただ映し出した。
「君の恐れも望みも、この鏡に写っているのは、君のこころそのものだよ。」
幻想を抜けると、地平線から「太陽」が昇った。
愚者は、その光の中で立ち上がる。
すべてが照らされ、傷も、後悔も、愛も、ぜんぶ見えていた。
でも愚者は逃げなかった。
「太陽」は言う。「見えることは、癒えることに近づく第一歩だよ。」
そして、遠くから「審判」の音が響く。
それは、誰かの呼び声。どこかで失われた記憶の再生。
愚者は過去と対話する。忘れていた痛み、選んだ道、別れた声。
審判は言う。「君が歩いてきた道が、君を呼んでいる。答えを出すのではなく、応えるのだ。」
その瞬間、愚者の中に風が走った。
時間も場所も、すべてが重なってひとつになるような感覚。
そして、足元に広がる「世界」。
輪が満ち、すべての扉が開いている。
誰もがそこにいて、誰もがいなかった。
始まりも、終わりも、意味ではなく存在になった。
愚者は笑った。あの時、はじまりの風に背中を押されてから、ずっと探していた“場所”がここにあった。
けれど彼は気づく。
「世界」は終わりではない。
それは、“ひとつになった存在”が、また歩き出すための新たなはじまり。
彼の背に、風がふたたび吹く。
物語は、再びめぐっていく。
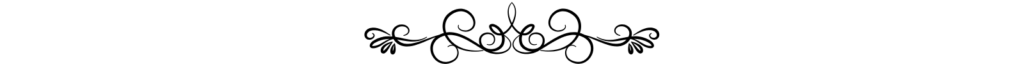
- 星:叶える力の在りか
- 星:願いが遠くに感じるとき
- 月:揺らぐ鏡の奥
- 月:幻想が晴れるとき
- 太陽:すべてが照らされる
- 太陽:光を失うとき
- 審判:呼びかけに応える
- 審判:その声が届かない
- 世界:ひとつにつながる
- 世界:巡りなおす旅
この章が語るものは終わりました──でも、旅路の扉はまだ開かれています。